
「借金のカタ」として売られることになった詠。
信じていた母親にも裏切られた彼女は絶望の底へと叩きつけられる。
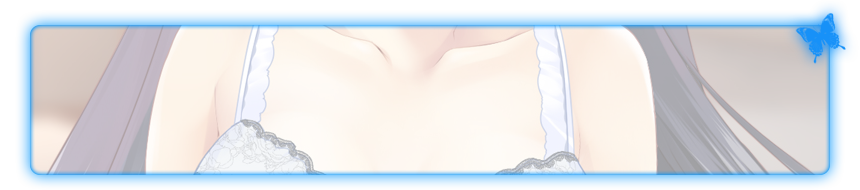
画像をクリックすると体験版シーンプレビューへ戻ります。
「…………」
家に帰ってきた私は、クソ親父の靴と
見慣れない靴があるのを見て、顔をしかめる。
誰か来てるんだ……。
やっぱり、学校で時間を潰せば良かったかもしれないな。
それにしてもあの女の子、一体なんだったんだろう?
この家のことを調べている、教育関係の人とか?
もしくは探偵? けど、あんな女の子がどうして?
だめだ……全然わからない。
もしかしたら、盗聴されてたり?
……ま、歌音以外の人間なんて
別にどうでもいいんだけど。
「……え?」
そう考えつつ、部屋の扉を開けると。
「ああ、お、おかえり詠」「このガキか?」
「は、はい。そうです。どうですか?可愛いでしょ、ね?」「オレの趣味じゃぇが……ま、そのスジのヤツには
ウケるかもな」
クソ親父と、見慣れない男がいた。
「ちょっと……何?話なら、リビングでしてもらえる?」
「あぁ?んだと……お客に、いらっしゃいませも
言えねぇのか、このガキは」
「フン、オレは生意気なガキは趣味じゃねぇんだが。
どうするかな……」
「チャラ……?ちょっと、一体なんの話してんの?」
なんだか、すごいイヤな予感がする。
この男、さっきから私のことを値踏みするみたいに
ジロジロ見てきているし……。
「……そっちが出て行かないならいい。
私、外へ行ってくるから」
出来るだけ平静を装いつつ、
【詠】
【詠】
【男】
【父親】【男】
【詠】
【男】
【男】
【詠】
【詠】
部屋を出て行こうとすると。
「待てよ」
「痛っ……ちょ、ちょっと、離してっ……!」
思い切り、肩を掴まれてしまう。
「近くで見ると、確かに顔は整ってんな……。
おい、いいだろ?」
試す? 試すって、何を?
もしかして―――
「い、いや……いやぁっ!」
※本シーンにつきましては、製品版にてお楽しみください。
「……よっと」
「んくっ、あ……っ……」
男は私の中からペニスを抜くと、
ティッシュを取り、自分についた汚れを拭う。
そしてベッドでへたりきっている私へと一瞥もくれぬまま、
無言で部屋を後にした。
「ど、どうでしたか……?扉の向こうで様子を窺っていたのか、クソ親父の声がする。
「あぁ?楽しんだだと?バカかテメェ……。
面倒くせぇ躾しやがってよ!」
「……ま。けど、仕込めば使い物にはなんだろ」
「そ、それじゃあ、借金は!」そっか。やっぱり借金のカタ……ね。
まるで、昔の映画みたい。
あれだけ私の身体を好き勝手して楽しんだくせに。
……ううん、違うか。
私はクソ親父が楽しむだけの道具だっただけ。
ただのオモチャとなんら変わりない。
「奥さんもそれでいいか?」
【男】
【詠】
【男】
【詠】
【男】
【詠】
【男】
【男】
【父親】【男】
「なっ……!」
あ、あの人も、そこにいた……の?
扉1枚隔てられた場所で、
私がされているのを、ずっと聞いて……?
「……ええ。お願いします。
これでウチの中もせいせいするわ」
「……え?」
今……お母さん、なんて……?
「目ざわりなのよ、あの子……そもそも、こっちはいままで
育ててやったのよ? 身体でもなんでも売って、
わたし達の役に立つのは当然じゃない」
身体でも、なんでも……?
聞き間違えじゃ、ない……よね?
「ククッ……そーかいそーかい。なら、話は決まりだぜ。
準備できたらまた来るから、それまでは家族水入らずの
団らんを楽しめよ。な?」
扉の向こうから音がしなくなり、部屋が無音に沈み込む。
「うぅ……、ひぐっ……ぐっ、うう……」
【詠】
【母親】
【詠】
【母親】
【男】
【詠】
嗚咽が、漏れていた。
悲しい、悔しい、恨めしい……様々な感情が
ない交ぜになっていて、自分でもわけがわからない。
見て見ぬフリをしているのは、知ってた。
それでも、今はちょっとおかしくなっているだけで。
本当は、お父さんが生きていた時みたいに……。
子供の頃みたいに、私を愛してくれているんだろうって。
そう思っていた。
なのに。
なのに……!
「くっ、ううううっ……!ううぅっ、うああああっ……!」
布団に潜り、精一杯の声を上げる。
誰か、助けて欲しい。
誰か、私を見つけて欲しい。
こんな現実から逃がしてくれるなら、
それが誰だって構わない。
誰か。誰か。誰か―――
「うるさいわねっ!静かになさいっ!」
「っ!?」
扉を叩いた衝撃に部屋が震えた。
その震えは、そのまま私の小さい嗚咽へと変わる。
「うっ、ううっ、くぅぅっ、うううぅぅぅぅっ……!」
この期に及んで、何を恐れているのだろうか。
母親の言葉を素直に聞いた私は、
声を我慢して小さくすすり泣くのだった。
【詠】
【母親】
【詠】
【詠】